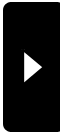2007年02月13日
The Last Words
「The Last Words」 とは2005年11月にこの世を去った、ピーター・F・ドラッカーに日本の出版社が最後にインタビューした内容をまとめた本で、「ドラッカーの遺言」というタイトルで出版されています。
大きくは6章で構成されているのですが、1ページ1テーマで書かれているので非常に読みやすくなっています。中身はその分濃いように思います。
今後起きるであろう変化やそのような変化にどう対応するかについて簡潔に書かれているように思います。
何度も読み返す必要があるように思います。
今日は「第3章”仕事”に起こった変化」から少しだけ紹介します。
大きくは6章で構成されているのですが、1ページ1テーマで書かれているので非常に読みやすくなっています。中身はその分濃いように思います。
今後起きるであろう変化やそのような変化にどう対応するかについて簡潔に書かれているように思います。
何度も読み返す必要があるように思います。
今日は「第3章”仕事”に起こった変化」から少しだけ紹介します。
日本の労働市場で進行しつつある変化。
それは「労働の質」と「労働を担う世代」の両面で変化。
労働の質は、「労働集約」的な仕事への重みから、頭脳集約的な仕事つまり「知識労働」が重要性を増し、グローバル競争を勝ち抜くための指標は「知識労働における生産性」で、その傾向が益々強まっている。
労働を担う世代では、最近テレビで話題になったように若年層の減少で定年が更に延長されていくなど、労働者の一層の高齢化が進むだろう。
といった感じです。
最後の章では、知識社会を生きるために、「自らをイノベートせよ」と言っています。常に学習することが必要とのことです。何故なら「知識が学習を要求する」からです。
学校を卒業したときから、学習が始まるとまで言っています。
言われてみれば、確かにそんな世の中になってきているようですね。
それは「労働の質」と「労働を担う世代」の両面で変化。
労働の質は、「労働集約」的な仕事への重みから、頭脳集約的な仕事つまり「知識労働」が重要性を増し、グローバル競争を勝ち抜くための指標は「知識労働における生産性」で、その傾向が益々強まっている。
労働を担う世代では、最近テレビで話題になったように若年層の減少で定年が更に延長されていくなど、労働者の一層の高齢化が進むだろう。
といった感じです。
最後の章では、知識社会を生きるために、「自らをイノベートせよ」と言っています。常に学習することが必要とのことです。何故なら「知識が学習を要求する」からです。
学校を卒業したときから、学習が始まるとまで言っています。
言われてみれば、確かにそんな世の中になってきているようですね。
Posted by Ryou-chan at 22:39│Comments(2)
│心に残った本
この記事へのコメント
ぼくの尊敬する師匠の竹田先生は、ドラッカー先生の本をテープに吹き込んで50回聞いたときに、全部わかったそうです。そんなぼくは毎日竹田先生のテープを聞いています。
Posted by 鈴木しゅんじ at 2007年02月15日 14:51
鈴木しゅんじ さん
コメントありがとうございます。
ランチェスターの竹田先生がドラッカーに
そこまで打ち込まれているとは。
確かにドラッカーの言葉は、当たり前そうでスーット目や耳に入りそうですが、自分のもにしようとすると難しいように感じます。
竹田先生で50回なら私は・・・・回か。
気が遠くなりそうですね。
コメントありがとうございます。
ランチェスターの竹田先生がドラッカーに
そこまで打ち込まれているとは。
確かにドラッカーの言葉は、当たり前そうでスーット目や耳に入りそうですが、自分のもにしようとすると難しいように感じます。
竹田先生で50回なら私は・・・・回か。
気が遠くなりそうですね。
Posted by Ryou-chan at 2007年02月15日 23:08