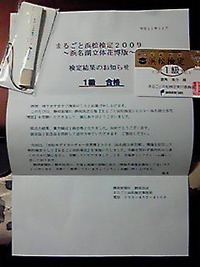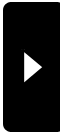2006年10月27日
江戸時代はものづくりの原点

今日、「浜松発!ものづくり講演会」が催された、経産省の方と国立科学博物館の方の2つの講演を聴きました。
このお二人の話から、学んだことは江戸時代は日本のものづくり力を育んだ時代だったということです。
江戸時代は、鎖国の時代でもあったわけですが、鎖国がむしろ日本独特の文化を生まれさせ、ものづくりの面でも究極のリサイクル社会を作りだし、現場主義に根ざした技術を生み出した時代でもあったようです。
鎖国政策のお陰で、他国から侵略されることもなく、また藩制度で藩として生き残るためによい意味の競争が行われたことがその背景にあるようです。
面白い比較として紹介されたのは、鉱山の風景を描写した絵でした。
海外の鉱山の絵は、階級が明確で、鉱石を掘る人、精錬する人、加工する人、利用する人が階層でで描かれているのに対し、日本の鉱山の絵は、階級がなく、鉱山の横に相撲をして興じている絵が付いているとのことです。講師の方は福利厚生まで考えられていると解説されていました。また金属を精錬する絵では、海外が立ってしかも男だけで作業しているのに対し、日本では座ってしかも男女で作業をしている絵になっていました。
つまり、江戸時代日本では、職人は殿様のためのものを作る一方で、その技術を社会に還元していた。職人の地位も高かったようです。海外から入ってきたものを、日本流にアレンジしたりするのが特に旨かったようです。 空気銃が輸入されると、輸入品よりも優れた銃を真似て作るだけでなく、その技術を応用して空気で油を補給する万年灯という油台を作ったりしたそうです。
このように、江戸時代のものづくり技術は群を抜いていたようです。
昨年東芝が、創業130年を記念して創業者の田中久重が1851年に制作した一度動かすと一年間時を刻む万年時計(写真)を再現したそうです。しかし、装飾の一部は、レントゲンで調べ製造方法は分かってもそれと同じように再現することは出来なかったそうです。
年々、工学部の学生が減少しているそうですが、日本人に流れるものづくりへの情熱と技術をきっちりと受け継いでいくことがとても重要な気がしました。そして現在の日本の優れた工業製品を支えているのは、鍛造、鋳造、プレス、金型、メッキ、金属加工など主として零細の中小企業の技術だそうです。 我々は、もっと歴史に学ぶ必要がありますし、技術力ある中小企業にもっと目を向ける必要がありそうです。
Posted by Ryou-chan at 23:07│Comments(14)
│お勉強
この記事へのコメント
放置日本ブランドニュースより抜粋
日立金属(5486)が世界最強といわれる日本刀の技術を応用して開発した、S-MAGICという特殊鋼が金型作りを行う中小企業に人気を呼んでいる。Y製作所のY社長によると、切れ味抜群で北米向けの自動車用プレス金型に好評を得ているとのこと。うちの精度重視のものづくりの考え方が本質的にマッチしているとも。
きっとこの材料の開発者は江戸のものづくりの原点を見極めていたのだろう。
日立金属(5486)が世界最強といわれる日本刀の技術を応用して開発した、S-MAGICという特殊鋼が金型作りを行う中小企業に人気を呼んでいる。Y製作所のY社長によると、切れ味抜群で北米向けの自動車用プレス金型に好評を得ているとのこと。うちの精度重視のものづくりの考え方が本質的にマッチしているとも。
きっとこの材料の開発者は江戸のものづくりの原点を見極めていたのだろう。
Posted by マツダ小僧 at 2008年03月27日 21:36
マツダ小僧さん
コメントありがとうございます。
恐らく江戸時代の職人は、現代のような分析技術や理論を知らないわけで、鉄を伝統で受け継がれた経験と色や臭いや手で触った感触など、文字通り五感で理解していたのでしょうね。
コメントありがとうございます。
恐らく江戸時代の職人は、現代のような分析技術や理論を知らないわけで、鉄を伝統で受け継がれた経験と色や臭いや手で触った感触など、文字通り五感で理解していたのでしょうね。
Posted by Ryou-chan at 2008年03月27日 22:11
日立金属の特殊鋼といえば、昔は出雲の国と呼ばれた島根県の安来市にありますよね。
「出雲の鐵は日立の鍛人(かぬち)のたまものなり。」といわれたほどで、戦時中は陸軍と海軍が高性能な特殊鋼を奪い合っていたという話をよんだことがあります。
「出雲の鐵は日立の鍛人(かぬち)のたまものなり。」といわれたほどで、戦時中は陸軍と海軍が高性能な特殊鋼を奪い合っていたという話をよんだことがあります。
Posted by 古事記 at 2008年03月30日 13:23
今月号のプレス技術を読んでいましたら、次世代SKD11のS-MAGICを開発しているということに気がつきました。大学の金属の先生に知り合いがいるので、聞いたら金属系の関係者の間では超多元系合金設計に成功した材料として結構有名だったのでつかってみると、なんとSKD11の2倍の突き出し量で削ってもOKだった。材質でも振動って変わるもんなんですね。
Posted by トヨタマ at 2008年04月18日 21:17
その材料の開発者って2chで「白鯨」って小説のエイハブ船長のようだと評されていた人物ではないでしょうか。
なんかそのような話を、又聞きすると、中島みゆきの「宙船」の歌詞を思い出してしまいます。
なんかそのような話を、又聞きすると、中島みゆきの「宙船」の歌詞を思い出してしまいます。
Posted by 皆木 at 2008年09月22日 16:24
噂に名高きSKD11に替わる次世代旗艦鋼種ですね。なんだか、大物の斬鉄剣なんか作ってみたくなりますね。
Posted by 「地上の星」ファン at 2008年10月09日 19:14
安来のアモルファス工場は凄いそうだ。いろんな人材が集まってるらしい。
Posted by みこと at 2015年06月06日 21:38
今年5月定年まで勤め上げられた方は、本当に凄く素晴らしい人らしい。知る人ぞ知る。
Posted by 佐野 at 2015年06月11日 18:27
炉長をしておられた先輩。僕も若い頃、救われた。どうか65歳まで辞めないで下さい。
Posted by 柴田 at 2015年06月11日 19:25
あの日立安来を定年まで勤め上げるということは、並大抵の事じゃない。尊敬できる人なのです。
Posted by 田中 at 2015年06月11日 19:43
安来アモルファスのただ一人のシニア社員先輩には、凄く面倒を見てもらいました。どうか、お元気で。感謝しています。
Posted by 黒竹 at 2015年10月28日 22:35
山陰の安来にはそんなにも凄いエリアがあるんですね。”ゲゲゲの女房”松下奈緒さんが演じてた人のふるさと。凄い伝統を持つハガネの街ですね。
Posted by 岐阜 at 2015年11月15日 21:04
アモルファストランスは損失が従来の6分に1になる、これからは、アモルファストランスの時代になるだろう。
Posted by 大阪 at 2016年02月18日 18:04
日立安来アモルファスとファインメットが一つになったらしい。人材交流が進み、さらに、進化するだろう。
Posted by 横浜 at 2016年03月04日 20:42