2006年09月21日
人事制度改革がもたらしたもの
昨日、懇意にさせていただいている社長さんとお話をする機会がありました。
社員に働きやすい環境をつくり、社員自身の成長と仕事の質を上げることが
会社の業績にもつながると考えておられる社長さんで、お話しするたびに
何らかの刺激をいただけるのでいつも感謝をしています。
その社長さんから、生産性新聞(2006.9.15)の記事の切抜きをいただきました。
その記事は、経済産業省が委託した「人材に関する研究会」の報告書についてでした。
その報告書の骨子を少し紹介(編集しています)しますと
90年代以降の企業の人事施策はコスト削減には効果があったが、組織・チーム力の低下や人材育成機能の低下などの問題も顕在化しており、今後は人材の成長を中心に据えたマネジメントが重要だと指摘してます。
成果主義に人事評価制度を変えた企業が多く見られましたが、本当に当初の狙いを果たしたのか。資源の適正配分については一定の効果が得られたものの、社員のモラールアップや業績向上に関しては思うように効果は上がっていない。
一方で成果主義の導入により予想していなかった問題点
社員に働きやすい環境をつくり、社員自身の成長と仕事の質を上げることが
会社の業績にもつながると考えておられる社長さんで、お話しするたびに
何らかの刺激をいただけるのでいつも感謝をしています。
その社長さんから、生産性新聞(2006.9.15)の記事の切抜きをいただきました。
その記事は、経済産業省が委託した「人材に関する研究会」の報告書についてでした。
その報告書の骨子を少し紹介(編集しています)しますと
90年代以降の企業の人事施策はコスト削減には効果があったが、組織・チーム力の低下や人材育成機能の低下などの問題も顕在化しており、今後は人材の成長を中心に据えたマネジメントが重要だと指摘してます。
成果主義に人事評価制度を変えた企業が多く見られましたが、本当に当初の狙いを果たしたのか。資源の適正配分については一定の効果が得られたものの、社員のモラールアップや業績向上に関しては思うように効果は上がっていない。
一方で成果主義の導入により予想していなかった問題点
(納得感の低下=仕事の細分化・個人化、個人間競争によるチーム力の低下、組織統合力の低下。人材育成機能の低下=能力向上インセンティブの低下、偏った目標管理による挑戦の阻害。現場の疲弊とプロセス管理の弱体化)も浮き彫りになっている。
これは人材マネジメントを①人材の能力を高め、②能力の高まった人材に仕事を割り振り、③仕事の成果を評価し、④さらに評価結果を賃金やポストなど処遇に結びつける、のステップを繰り返すこととすると、これまでの成果主義的な改革は後工程、つまり成果の評価と処遇に結びつける仕組みの変化であったといえる。
だが人材マネジメントには前工程(人材が成果を出すまでのプロセス)がある。
成果主義とは前工程まで含めての変化であるべきなのにもかかわらず、多くの企業で導入された成果主義は評価賃金制度の変化にとどまってきたのである。働く人のモチベーションを高める機会の損失につながったといえる。
となっていました。
確かにこの報告の骨子を見ると、「成果主義」は人を育てより大きな成果を生み出すというよりも、おりしもデフレ不況の真っ只中ということもあり限られた人件費を配分するための手段として各企業がこぞって導入したような印象が強かったのではないでしょうか。
そう考えると、成果主義は人件費を抑制するという面では効果があったものの、社員の能力を向上させるという面では効果がほとんどなかったといえます。むしろ、個人の成果を優先するあまりチームとしての総合力が弱くなるという弊害すらあったようです。
おりしも2007年問題で技能継承が大きな課題になっていますが、人は短期間で育つことが難しいとすれば、なおさら人材育成を体系的に行うことが重要といえます。
なぜ給料を払いながら、社員の育成までしなければならないのかという疑問があるかもしれませんが、
企業の目指す価値観を共有し行動できる社員がどれだけ多くいるかが、企業の競争力を高め、業務の質を上げるとするならば、社員を育成することはもっとも効率的な投資と言えるのではないでしょうか。
そして、そのためのリーダシップやリーダーとしての魅力、度量、厳しさと優しさなども要求されることになると思われますので、自分を成長させることが社員を成長させることにつながるような気がします。
参考:
「人材マネジメントに関する研究会」報告書
http://www.meti.go.jp/press/20060810006/20060810006.html
これは人材マネジメントを①人材の能力を高め、②能力の高まった人材に仕事を割り振り、③仕事の成果を評価し、④さらに評価結果を賃金やポストなど処遇に結びつける、のステップを繰り返すこととすると、これまでの成果主義的な改革は後工程、つまり成果の評価と処遇に結びつける仕組みの変化であったといえる。
だが人材マネジメントには前工程(人材が成果を出すまでのプロセス)がある。
成果主義とは前工程まで含めての変化であるべきなのにもかかわらず、多くの企業で導入された成果主義は評価賃金制度の変化にとどまってきたのである。働く人のモチベーションを高める機会の損失につながったといえる。
となっていました。
確かにこの報告の骨子を見ると、「成果主義」は人を育てより大きな成果を生み出すというよりも、おりしもデフレ不況の真っ只中ということもあり限られた人件費を配分するための手段として各企業がこぞって導入したような印象が強かったのではないでしょうか。
そう考えると、成果主義は人件費を抑制するという面では効果があったものの、社員の能力を向上させるという面では効果がほとんどなかったといえます。むしろ、個人の成果を優先するあまりチームとしての総合力が弱くなるという弊害すらあったようです。
おりしも2007年問題で技能継承が大きな課題になっていますが、人は短期間で育つことが難しいとすれば、なおさら人材育成を体系的に行うことが重要といえます。
なぜ給料を払いながら、社員の育成までしなければならないのかという疑問があるかもしれませんが、
企業の目指す価値観を共有し行動できる社員がどれだけ多くいるかが、企業の競争力を高め、業務の質を上げるとするならば、社員を育成することはもっとも効率的な投資と言えるのではないでしょうか。
そして、そのためのリーダシップやリーダーとしての魅力、度量、厳しさと優しさなども要求されることになると思われますので、自分を成長させることが社員を成長させることにつながるような気がします。
参考:
「人材マネジメントに関する研究会」報告書
http://www.meti.go.jp/press/20060810006/20060810006.html
Posted by Ryou-chan at 22:21│Comments(0)
│新聞記事から
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|











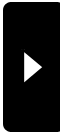
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。