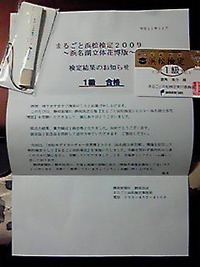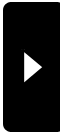2008年10月17日
今日は防災の分科会

全国地域情報化推進セミナーは「市民協働」と「防災」の二つの分科会に分かれて開催。
BCP(事業継続)に取り組んでいる私は、当然防災の分科会に参加。
約2時間半近く、パネルディスカッションが行われた。
コーディネータは東海大学の 小林 准教授
パネリストは 西宮市のCIO補佐官 吉田稔氏、岐阜市の仲家秀樹氏、静岡県地域情報化コーディネータの早瀬公夫氏
やはり、迫力があったのは阪神淡路大震災の経験のある西宮市の取り組みであった。
優れた防災システムが出来た背景には、①災害時の人的被害を最小にするという住民の人命を第一義に考えた防災システムへの想い、②ベンダー任せでなく市の職員が中心になってシステムづくりを進めたこと、③大震災での貴重な体験(防災システムに何が必要か)があったように思う。
BCPに関心の高い私は、西宮市の話をもっと聞きたいと思った。
パネルディスカッションでは、防災システムを推進する上で、自治体と住民、自治体と企業、自治体など支援側の組織間の壁が最大の問題ということで認識が一致していた。
確かに難しい問題ではあるが、地域住民の命や安全を守るという強い思いとリーダシップがあればやがてこの壁は低くなるのではと感じた。実際、西宮市が優れた防災システムを実現できたのもこのことを証明しているように感じた。
なんでも西宮市の防災システムは、他の自治体が自由に利用できる自治体主導によるシステムライブラリの第一号とのことだそうだ。
ただこの防災システムを実際に機能させるには、万が一の時住民側もこのシステムを積極的に活用したり、事実情報を正確に投稿するなどの協力が重要になるといえそうだ。
参考:西宮市の防災システムなどの情報
http://www.nishi.or.jp/homepage/museum/pamphlet/index.html
Posted by Ryou-chan at 09:36│Comments(0)
│お勉強