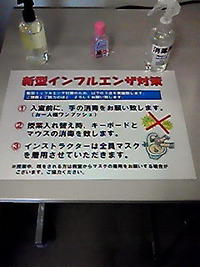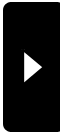2009年05月17日
新型インフルエンザの国内感染者が44人に
この土日で急に国内感染者が増加した。17日の19時過ぎには44人の発症者との報道があった。
今までは空港での水際対策が機能しているように見えていたが、結果からはやはりどこかで漏れがあったようだ。
別の見方をすると、
潜伏期間からみて水際で確実にチェックをすることの難しさを示しているといえる。
今回は弱毒型の新型インフルエンザだから比較的その影響は少ないかも知れないが、もし当初想定していたH5N1の強毒型の新型インフルエンザだったらと考えると多くの教訓を残したことになる。
日本から発生することは考えられないので、大阪や神戸の高校生は、家族ないしは比較的親しい間柄の海外からの帰国者からの感染しか考えられない。(現時点では感染経路は特定出来ていないが)
もしそうだとしたら、教訓としては「空港では発熱だけでなく、どこかに1週間程度停留しておくしか方法が無いことになる。」本来、空港で発熱チェックして問題がなければ、空港で記入した連絡先に定期的に連絡をし体調の確認を行う、また1週間程度は極力外出を避けるということになっていたはずだが、今回の結果からはこれが機能しなかったことを示している。
改めて、新型インフルエンザへの対策の難しさを実感させられた。国民全員が同じ問題意識で行動しない限り、対策だけでは限界があることを示したのだから。
中国が今回実施したように有無を言わさず関係者を停留する方法が最善だとすると、今後必ず発生すると言われている強毒型のインフルエンザを想定したBCPは、今回の教訓をもとに見直す必要がありそうだ。
Posted by Ryou-chan at 22:21│Comments(7)
│事業継続
この記事へのコメント
水際対策の目的は、 「インフルエンザの感染を抑え込み、日本にインフルエンザを上陸させない」だとお考えでしょうか? だとしたら、それはまず無理というものでしょう。日本にはハブ空港になっているところもあり、日本に入国しないで経由するだけの人もいます。でも、それは感染拡大の可能性はあります。
水際対策の目的は、上陸を遅らせ、その間にワクチンの準備など対策をすることではないでしょうか? 感染が広まったことは残念ですが、水際対策は効果があったと思います。今後は個人レベルの対策に切り替えていくべきでしょう。
水際対策の目的は、上陸を遅らせ、その間にワクチンの準備など対策をすることではないでしょうか? 感染が広まったことは残念ですが、水際対策は効果があったと思います。今後は個人レベルの対策に切り替えていくべきでしょう。
Posted by Bronco at 2009年05月18日 21:49
Broncoさん
コメントありがとうございます。
私自身もご指摘のように、日本の水際対策は、対応の早さ、徹底度、確実性どれをとっても世界中で一番優れていたと感じています。
しかし結果から見ると、水際対策の限界が明らかになったように思います。
入国時に発症していないが、保因者で潜伏期間にある人への対策を見直す必要があるとの考えです。
企業では、海外からの帰国者は一定期間出社させず、在宅勤務をさせるという対策が必要かも知れません。
19日の新聞には、欧州の国では保菌が疑われる段階で、抗インフルエンザ薬の服用をすることで2次感染を押さえ込んでいるという記事がありましたがこれも有効かも知れません。
どちらにしても、連絡先を記入し、フォローするという仕組みが機能しないことは証明されたといえるでしょう。
もしH5N1でこれがおきたら、経済活動が停止しかねないだけに、国家としてのBCPとしても真剣に考える必要があるでしょうし、企業にとってもインフルエンザ対策のBCPを見直す必要があるといえるのではないでしょうか。
コメントありがとうございます。
私自身もご指摘のように、日本の水際対策は、対応の早さ、徹底度、確実性どれをとっても世界中で一番優れていたと感じています。
しかし結果から見ると、水際対策の限界が明らかになったように思います。
入国時に発症していないが、保因者で潜伏期間にある人への対策を見直す必要があるとの考えです。
企業では、海外からの帰国者は一定期間出社させず、在宅勤務をさせるという対策が必要かも知れません。
19日の新聞には、欧州の国では保菌が疑われる段階で、抗インフルエンザ薬の服用をすることで2次感染を押さえ込んでいるという記事がありましたがこれも有効かも知れません。
どちらにしても、連絡先を記入し、フォローするという仕組みが機能しないことは証明されたといえるでしょう。
もしH5N1でこれがおきたら、経済活動が停止しかねないだけに、国家としてのBCPとしても真剣に考える必要があるでしょうし、企業にとってもインフルエンザ対策のBCPを見直す必要があるといえるのではないでしょうか。
Posted by Ryou-chan at 2009年05月19日 08:47
思うに対策のレベルを引き上げ過ぎでしょう。まず、今回の日本の水際対策は、対象が感染者が出た国からの直行便に限定されていました。そのため、感染者でも
(1) 第三国のハブ空港を経由して来た人
(2) 日本のハブ空港に立ち寄り、日本の土は踏んだけれども入国はせず経由しただけで、そのまま他国へ行った人
は対象ではありませんでした。もしも上記まで対象を拡大してしまうと、(1)では対象者が多くなり過ぎる、(2)では日本の空港がハブ機能を持てなくなる、という問題が発生します。これは経済活動の停止になります。そのため、この対策は現実的ではないのです。
(1) 第三国のハブ空港を経由して来た人
(2) 日本のハブ空港に立ち寄り、日本の土は踏んだけれども入国はせず経由しただけで、そのまま他国へ行った人
は対象ではありませんでした。もしも上記まで対象を拡大してしまうと、(1)では対象者が多くなり過ぎる、(2)では日本の空港がハブ機能を持てなくなる、という問題が発生します。これは経済活動の停止になります。そのため、この対策は現実的ではないのです。
Posted by Bronco at 2009年05月19日 21:38
対策が行き過ぎかどうかは、今回のH1N1が幸い弱毒であり病原性が低かったからいえることではないでしょうか。
これがもし、当初想定のH5N1の強毒性のインフルエンザであったらと考えると、空恐ろしくなります。おそらく今頃は経済を含め大変な事態になっていたといえます。その意味で感染地から帰国した人は国内で感染の切欠を作らないというそれなりの責任感を持っていただかないと困ると言うことです。自分だけの問題では無いと言うことです。おそらく今回の関西での問題も、1人の海外帰国者のこれくらいはといった不注意な行動がもたらしたものでしょう。このような無責任者がいるかぎり、ひとまとめで停留という手段もやむなしとなりかねないですよね。
対策にやり過ぎは無いと思います。その想定したリスクへの対策を、状況に合わせ適格に発動でき、関係者がその対策の意味を理解した上で確実に実行できることこそが重要といえます。(水際対策では、発熱などの発症が疑われる人は隔離し、発症・発熱のない人は、連絡が取れることを条件に入国を許可し、基本的には1週間程度は外出・出社を自粛し、もし発熱や体調不良の場合は保健所に連絡する体制となっていましたが、結果からはこれが機能しなかった)
BCPで想定した通りに現実の事象は進行しないことは、今回の事例でも明らかです。しかし、事前にリスクを想定しその上で対策を考え、定期的に訓練を繰り返すことで、想定外の事象への応用力が養われると考えています。(今回はこの想定外の事象が高校のスポーツ交流で起こったわけです、また地域の病院からインフルエンザ症状らしい患者の検体を、海外渡航歴がないということで検査が後回しになったという事象にも繋がっていたように思います)
経済、自然災害、感染症と企業を取り巻くリスクは無数にありますそこで、自社の経営に及ぼすリスクを評価しその対策をあらかじめ検討しておくBCPへの取組が経営戦略の重要な一つとして認識され、機密事項として取り組まれている所以でもあります。社員の雇用を守り、かつ命の大切さを思えば思うほど、リスクに目を配り、対応を考えておくことに真剣にならざるを得ないのではないでしょうか。そのことが結局は対策コストを低くし、もし事象が起きは場合でも被害範囲と被害額を最小にすることにつながるのではと思います。
これがもし、当初想定のH5N1の強毒性のインフルエンザであったらと考えると、空恐ろしくなります。おそらく今頃は経済を含め大変な事態になっていたといえます。その意味で感染地から帰国した人は国内で感染の切欠を作らないというそれなりの責任感を持っていただかないと困ると言うことです。自分だけの問題では無いと言うことです。おそらく今回の関西での問題も、1人の海外帰国者のこれくらいはといった不注意な行動がもたらしたものでしょう。このような無責任者がいるかぎり、ひとまとめで停留という手段もやむなしとなりかねないですよね。
対策にやり過ぎは無いと思います。その想定したリスクへの対策を、状況に合わせ適格に発動でき、関係者がその対策の意味を理解した上で確実に実行できることこそが重要といえます。(水際対策では、発熱などの発症が疑われる人は隔離し、発症・発熱のない人は、連絡が取れることを条件に入国を許可し、基本的には1週間程度は外出・出社を自粛し、もし発熱や体調不良の場合は保健所に連絡する体制となっていましたが、結果からはこれが機能しなかった)
BCPで想定した通りに現実の事象は進行しないことは、今回の事例でも明らかです。しかし、事前にリスクを想定しその上で対策を考え、定期的に訓練を繰り返すことで、想定外の事象への応用力が養われると考えています。(今回はこの想定外の事象が高校のスポーツ交流で起こったわけです、また地域の病院からインフルエンザ症状らしい患者の検体を、海外渡航歴がないということで検査が後回しになったという事象にも繋がっていたように思います)
経済、自然災害、感染症と企業を取り巻くリスクは無数にありますそこで、自社の経営に及ぼすリスクを評価しその対策をあらかじめ検討しておくBCPへの取組が経営戦略の重要な一つとして認識され、機密事項として取り組まれている所以でもあります。社員の雇用を守り、かつ命の大切さを思えば思うほど、リスクに目を配り、対応を考えておくことに真剣にならざるを得ないのではないでしょうか。そのことが結局は対策コストを低くし、もし事象が起きは場合でも被害範囲と被害額を最小にすることにつながるのではと思います。
Posted by Ryou-chan at 2009年05月20日 09:21
まず、本人に自覚を持たせるのは難しいだろうと思いますよ。初期段階では、感染者が出たかどうか、その情報を入手できないで帰国した人が大半でしょう。直行便ならともなく、第3国の経由の場合には特に情報入手が困難でした。
次に、感染が広がっていない段階で、対策を強化しすぎると、実質、ハブ空港は機能しなくなります。これは日本経済にも大きなダメージですが、それ以上に日本と貿易関係のある国へのダメージが大きいでしょう。その点はどうお考えですか?
日本は経済大国です。しかも貿易によって成り立っています。感染から日本国民を守ることも重要ですが、感染が広まっていない段階で、経済大国としての責任を果たせなくなってしまいませんか?
次に、感染が広がっていない段階で、対策を強化しすぎると、実質、ハブ空港は機能しなくなります。これは日本経済にも大きなダメージですが、それ以上に日本と貿易関係のある国へのダメージが大きいでしょう。その点はどうお考えですか?
日本は経済大国です。しかも貿易によって成り立っています。感染から日本国民を守ることも重要ですが、感染が広まっていない段階で、経済大国としての責任を果たせなくなってしまいませんか?
Posted by Bronco at 2009年05月20日 22:04
日本国内に滞在、あるいは帰国した人のことについて話しています。
また経済活動を止めろとも言っていません。
感染リスクがあるかも知れないということを自覚して、もし感染していた場合他人に感染させないよう注意しなさいといっています。
しかし悲しいかな、Broncoさんご指摘のようにそんな簡単なことすら出来ない人(自覚のない人、自覚を持とうと努力しない人)がいることも事実です。
そういう事態でも国民や組織をを守ろうとすると自覚のない人がいるという前提で対策を考えざるを得ないのではないでしょうか。
いみじくも、自覚の差は大阪・兵庫と八王子・川崎とを比べると明らかでしょう。
幸い今回は想定外の弱毒型のH1N1でしたが、もしH5N1の感染が拡大したら日本国内だけで64万人以上の人が死ぬと予測されていますが、それでも同じ行動を取られますか。
また経済活動を止めろとも言っていません。
感染リスクがあるかも知れないということを自覚して、もし感染していた場合他人に感染させないよう注意しなさいといっています。
しかし悲しいかな、Broncoさんご指摘のようにそんな簡単なことすら出来ない人(自覚のない人、自覚を持とうと努力しない人)がいることも事実です。
そういう事態でも国民や組織をを守ろうとすると自覚のない人がいるという前提で対策を考えざるを得ないのではないでしょうか。
いみじくも、自覚の差は大阪・兵庫と八王子・川崎とを比べると明らかでしょう。
幸い今回は想定外の弱毒型のH1N1でしたが、もしH5N1の感染が拡大したら日本国内だけで64万人以上の人が死ぬと予測されていますが、それでも同じ行動を取られますか。
Posted by Ryou-chan at 2009年05月21日 09:24
at 2009年05月21日 09:24
 at 2009年05月21日 09:24
at 2009年05月21日 09:24 時系列でしっかり整理してくだい。水際対策が有効なのは、海外で発生しているが、日本では感染者が出ていない段階ですよ。
この段階では、海外にいるとわかりますが、日本ほど情報がありません。ましてや言葉の問題もあって情報入手はかなり困難です。この状況では、自分が感染国を通過したかどうかを認識するのは困難です。既に行く前から感染者が出ているような状況であれば、自覚するのは簡単でしょうが。
たとえH5N1のインフルエンザが発生した場合であっても、日本で感染者が出ない段階でハブ空港の機能を停止させるようなことができるかは疑問です。
この段階では、海外にいるとわかりますが、日本ほど情報がありません。ましてや言葉の問題もあって情報入手はかなり困難です。この状況では、自分が感染国を通過したかどうかを認識するのは困難です。既に行く前から感染者が出ているような状況であれば、自覚するのは簡単でしょうが。
たとえH5N1のインフルエンザが発生した場合であっても、日本で感染者が出ない段階でハブ空港の機能を停止させるようなことができるかは疑問です。
Posted by Bronco at 2009年05月21日 22:25