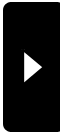2006年09月09日
外国人との共生が必要な訳

9月11日号の日経ビジネスの特集記事「こんな国では働けない-外国人労働者[使い捨て]の果て」がありました。
この特集記事の書き出しは
正社員と非正社員、ヒルズ族とニート。格差におびえるニッポン。
だが、我々の社会はもっと大きな格差を既に内包している。
外国人労働者・・・・・・・。
「きつい、汚い、危険」の3K職場や深夜のコンビニエンスストアは、
もはや彼ら抜きでは成り立たない。少子高齢化が始まったのに、まだこの国は彼らを本気で迎え入れる覚悟を決めていない。
「お金さえ払えばいくらでも来てくれる」と思ったら大間違い。
「こんな国では働けない」
彼らはニッポンに失望し、見切りを付けようとしている。
まずは彼らの肉声に耳を傾けて欲しい。
とあります。
私もある部品工場で業務改善の調査で現場周りをしたとき、少し違和感に感じたことが顕在化してきたように思いました。
その工場は24時間生産していることもあり夜勤はほとんど外国人労働者がメイン。昼間も合理化を進めてきたからか日本人の正社員は生産技術に管理業務や金型などのメンテナンス、現場作業は外国人労働者とパートのおばさん達が主体。だって今のニッポンには、現場仕事で何かを掴んで飛躍しようという気概のある若者はいないし、している仕事で人の価値を判断する傾向が強いように思います。
結局はモノづくりの現場で、品質や生産性をほんとに支えているのは実際に作業をしている人たちではと感じました。今はまだ、現場を経験した正社員もいるので指導ができると思いますが、管理業務を中心に経験してきた正社員が主力になった場合、モノづくりのノウハウは誰が持っているのかが問題になるように思います。現状では現場のノウハウは外国人の人々の中にあるようにように思います。
そう考えると、何か将来に大きな不安を感ぜずにはいられません。高品質がウリのニッポンの製造業も大きなリスクを抱えているように思います。
やはり、大切なのは外国人の方々もパート労働者もひとりの人間として接することではないでしょうか。けがや病気をすれば見捨てるといった「使い捨て」が、将来を明るくするとは思えません。一見合理的なように見える「使い捨て」は、自分たちの大切なものも同時に失っていくことに気づくべきではないでしょうか。
特集記事の結びは
外国人労働者や留学生アルバイトがいなければ深夜のコンビニエンスストアで買い物できないし、クリーニング店も利用できず、自動車も作れない。それが目の前にある現実だ。2015年までに日本の若年層は200万人以上減少するという、間違いなく事態は深刻化する。
門戸開放の是非を論ずる時期はとうに過ぎた。現実を直視し、共生の方法を考えるしかない。敢えて前向きに捉えるならば、それは均質ゆえに脆いこの国を、重層的でしなやかにするプロセスである。
となっていました。
結局はモノづくりの現場で、品質や生産性をほんとに支えているのは実際に作業をしている人たちではと感じました。今はまだ、現場を経験した正社員もいるので指導ができると思いますが、管理業務を中心に経験してきた正社員が主力になった場合、モノづくりのノウハウは誰が持っているのかが問題になるように思います。現状では現場のノウハウは外国人の人々の中にあるようにように思います。
そう考えると、何か将来に大きな不安を感ぜずにはいられません。高品質がウリのニッポンの製造業も大きなリスクを抱えているように思います。
やはり、大切なのは外国人の方々もパート労働者もひとりの人間として接することではないでしょうか。けがや病気をすれば見捨てるといった「使い捨て」が、将来を明るくするとは思えません。一見合理的なように見える「使い捨て」は、自分たちの大切なものも同時に失っていくことに気づくべきではないでしょうか。
特集記事の結びは
外国人労働者や留学生アルバイトがいなければ深夜のコンビニエンスストアで買い物できないし、クリーニング店も利用できず、自動車も作れない。それが目の前にある現実だ。2015年までに日本の若年層は200万人以上減少するという、間違いなく事態は深刻化する。
門戸開放の是非を論ずる時期はとうに過ぎた。現実を直視し、共生の方法を考えるしかない。敢えて前向きに捉えるならば、それは均質ゆえに脆いこの国を、重層的でしなやかにするプロセスである。
となっていました。
Posted by Ryou-chan at 17:52│Comments(0)
│日経ビジネスから